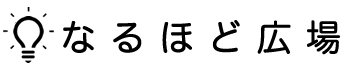金閣寺と銀閣寺のちがいを見た目から歴史的観点まで詳しく解説!
2017/03/14

京都を代表する建造物と言えば金閣寺、銀閣寺ではないでしょうか。
呼び名も似ているこの金閣寺と銀閣寺ですが、どんなちがいがあるのか気になりますよね。
ちがいを知ると建物の歴史背景も理解しやすいものです。ぜひご覧ください。
スポンサーリンク
こんな記事もよく読まれています
-

-
子供が算数の計算が苦手、そんな時に克服するための方法!
子供が算数が苦手で、どう教えたらいいのかと悩む親御さんも多い...
-

-
幼稚園でのバスのトラブルの賢い回避方法をご紹介します。
子供が幼稚園に通い始めバスでの通園になり楽になったと安心して...
-

-
妊婦さん必見!動悸が食後にする時にはこんな方法で改善を!
妊婦になるとお腹が大きくなることから、食後に動悸が起こるとい...
-

-
子供が父親になつかないと悩んだら、そんな時の解決方法!
子供が父親になつかない・・・そんなふうに悩んでいるお父さんや...
-

-
子供の性格の短所はどのように書く?長所よりも書きにくい!?
幼稚園の願書に子供の短所(性格)を書くときにはいったいどのよ...
-

-
子供に愛情がわかない…そんな時の解決策をご紹介します
子供に愛情がわかない…そんな悩みを抱えているお母さん、多いと...
-

-
産後、旦那の態度にイライラしてしまう原因についてご紹介します
なぜか産後、旦那の態度のイライラ・・・こんな気持ち私だけ?と...
-

-
産後なのに子宮の手術をする・・・その手術について解説します!
妊娠中の検査で子宮筋腫や卵巣の病気が見つかることがあると言い...
-

-
産後の子宮の違和感を感じる時は何かの病気!?
産後の子宮になんだか違和感を感じるのは気のせい?でもやっぱり...
-

-
産後のトイレの悩みは皆一緒!痛いけど我慢するともっと大変
産後は会陰切開で傷になっている痛みでトイレに不安を感じる人は...
-

-
赤ちゃんに着せる洋服の枚数ルールについて理解しよう!
赤ちゃんに着せる洋服の枚数って大人より少なくっていうけど、生...
-

-
赤ちゃんの風邪は治りかけに要注意!外出はひかえるのが望ましい
赤ちゃんが風邪をひくと、ママと一緒に家でおこもり…。もう飽き...
-

-
赤ちゃんの泣き声でノイローゼにならないお母さんはこうしてる
赤ちゃんの泣き声で気が滅入る瞬間ってたくさんありますよね・・...
-

-
これって?大丈夫?赤ちゃんの顔に”毛細血管”が出やすい理由!
赤ちゃんの顔に赤いポツポツがある…これって一体…?と心配した...
-

-
経産婦でも初産でも本陣痛ってわからないものです
初産の妊婦さんでも経産婦さんでも陣痛ってよくわからないもので...
-

-
仕事のストレスによって流産しないために気を付けたいこと
仕事のストレスにより流産しないために…流産は必ずしもママに原...
-

-
ミルクと母乳の混合授乳のやり方の方法とコツについて
赤ちゃんが産まれたら母乳で育てたいと考えますよね。 い...
-

-
ベビーカーは電車で使ってもいい?それとも抱っこひもが正解?
電車ではベビーカーと抱っこひも、どちらを使うのが正解なのでし...
-

-
学校で友達に怪我をさせてしまった。その時にとる対応について
学校でお友達に怪我をさせてしまったらどのように対応していいの...
-

-
ピアノの才能・・・うちの子供にはある?ない?判断材料は何か!
ピアノ教室は、今も昔も人気の習い事です。 最初のうちは...
スポンサーリンク
この記事のあらすじ
金閣寺と銀閣寺のちがいは?
金閣寺と銀閣寺は呼び名こそ似ていますが、全く別のお寺です。そもそも正式名称は金閣寺が「鹿苑寺」、銀閣寺が「慈照寺」と言い、建てられている場所も同じ京都ではありますが、金閣寺は北部、銀閣寺は東部とお互いの距離は7kmほど離れているのです。
金閣寺が建てられたのは、足利義満が将軍を務めていた時代のことです。幕府の権力が強かった頃に、当時の日本文化と、貿易によって大陸から渡ってきた文化が混ざり合うことで生み出された新たな文化である「北山文化」を取り入れている建物の代表格でもあります。全部で三層から成り立っており、そのうちの二層には金箔が貼り付けられています。各階それぞれがどれも異なる方法で造られており、1階は寝殿造、2階は武家造、3階は禅宗様式が使われています。
銀閣寺は足利義政が将軍の座に就いていた時代に建てられました。この頃になると幕府の力も弱まってきており、各地を束ねる領主などと組むことで政治を取り仕切っていました。ちなみに銀閣寺は名前にこそ「銀」が入っていますが、実は銀箔を使っているわけではありません。シンプルで上品さを追求した「東山文化」の要素が大きく見られるもので、外壁には黒漆を塗り込み、1階には現在の建物の基本形ともなった書院造が用いられています。
金閣寺と銀閣寺の歴史的観点からするちがいとは?
金閣寺は足利義満が幕府の将軍となった時代に建てられたものです。
足利義満とは足利尊氏の孫であり、60年ほど続いていた南北朝時代をまとめていき、封建制度を作り上げることで、天皇よりも高い地位に君臨するようになりました。この時に禅と公家、大陸からもたらされた文化をひとつにした北山文化も広まるようになり、その代表として建築されたものが金閣寺なのです。義満が仏門に入った後は御所としての役割も果たしたと言われています。義満は天皇の位を奪い取ろうと考えていましたが、あと一歩で手が届くというところで急死してしまいます。それからは幕府の力は次第に失われていき、各地方を治めている領主達と共に日本を支えていきました。
当時の8代目となる足利義政でしたが、誰が跡継ぎになるのかという問題がきっかけで引き起こされた応仁の乱により、38歳の頃に自分の子供である義尚へとその座を譲りました。その後は京都の東山に籠もり、使えるだけのお金を使って銀閣寺を建てたとされています。これ以降、日本は戦いが中心となる戦国時代へと突入していくことになるのです。
金閣寺と銀閣寺とでは見た目でも大きなちがいがある
銀閣寺は金閣寺とは違い、見た目は特に銀色をしているわけではありません。しかしかつては銀閣寺にも銀箔が使われていたと言われています。ですが金閣寺のように外壁に貼られていたのではなく、建物の内側、それも2階の天井部分に銀箔を貼った跡が残っているとされています。銀閣寺は個人的な用事を済ませるための場所として利用されてきましたが、特に多かったものが「お月見」です。そしてこのお月見に、天井にある銀箔が役立っていたのです。
銀閣寺には「銀砂灘」と呼ばれる台が設置されており、室内に差し込んできた月明かりを反射させて、2階まで届ける役割を担っていました。すると銀箔に月明かりが当たり、キラキラと淡く光り輝きます。人々はそれを見るのを楽しみにしていたのです。現在も銀箔こそ残っていませんが、台はそのまま置いてあるので、昔と変わらず月明かりを天井まで届けているそうです。金閣寺と比べれば地味な印象を受けてしまう銀閣寺ですが、それこそ夜空を照らす月のように、静かで控えめな美しさを保っている建物なのです。
金閣寺を観光する場合は午前中がおすすめ?
京都は奈良と並んで世界遺産の宝庫と言っても過言ではないところですが、その中でも特に有名で、訪れる観光客が多いのは金閣寺ではないでしょうか。金箔が貼られた外壁は昼間でも明るく輝き、日本人だけではなく海外からやってきた人達をも魅了していると言われています。
観光する時間帯は午前中がおすすめです。これは少しでも人混みを避けられるようにという意味合いもありますが、金閣寺をぐるりと取り囲んでいる池に映る風景は、朝の澄み切った空気の中で見た方が、さらに美しく感じられるという理由も含まれています。天気が良ければ金閣寺も映り込み、いわゆる「逆さ金閣寺」も拝むことが出来るでしょう。
いつでも変わらない姿を披露してくれる金閣寺ですが、1950年に放火が原因で、全て焼け落ちてしまったという歴史があります。5年後に再建されたものの、貴重な素材の天井などが失われるなど損害も大きく、また犯人が若い僧侶であったという真実も世界中に衝撃を与えました。この放火事件をきっかけとした作品も出版されているので、事件について知らない人も、詳しいことを知りたいのならこれらの作品に手を付けてみると良いでしょう。
どうして銀閣寺には銀箔が貼られていないの?
銀閣寺には金閣寺と違って銀箔は貼られていません。昔は貼られていたが全て剥がれてしまった、貼る予定はあったが応仁の乱の影響で貼るための予算がなくなったなど、いろんな説が人々の間で囁かれていますが、実はこれらの話には根拠がないようなのです。
そもそも銀箔がかつて貼られていたと思われるようになったのは、江戸時代に出版された、現在で言うところのガイドブックのような本に「銀閣寺は金閣寺をお手本にした」と記載されていたからだと言われています。しかし足利義政が参考にした建物は、京都市の西京区にある西芳寺とされています。西芳寺には西来庵と呼ばれる建物があり、これを見本にしたものが銀閣寺に建てられた東求堂なので、銀閣寺の中心となるのはこちらの東求堂であるという意見を持つ人も存在します。また観音殿のことを「銀閣」と称したのも江戸時代のことなのです。
観音殿は幕府の将軍の自宅に建てられた建物のことを指す言葉なので、決して銀閣だけを示すものではありません。それは金閣寺を建立した足利義満の家も例外ではなかったため、銀閣と比較するのなら、金閣よりも観音殿の方がしっくり来ると言えるでしょう。